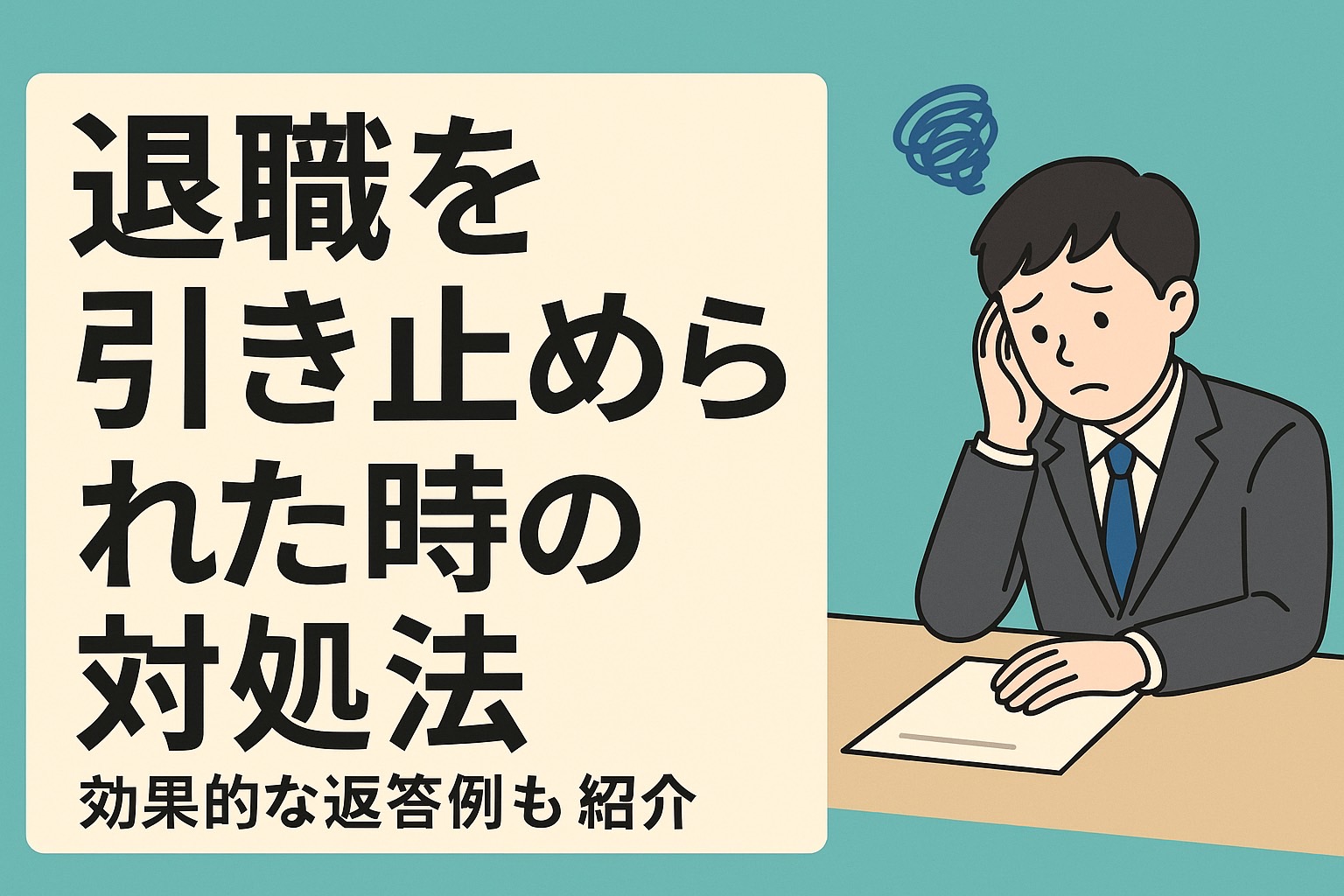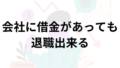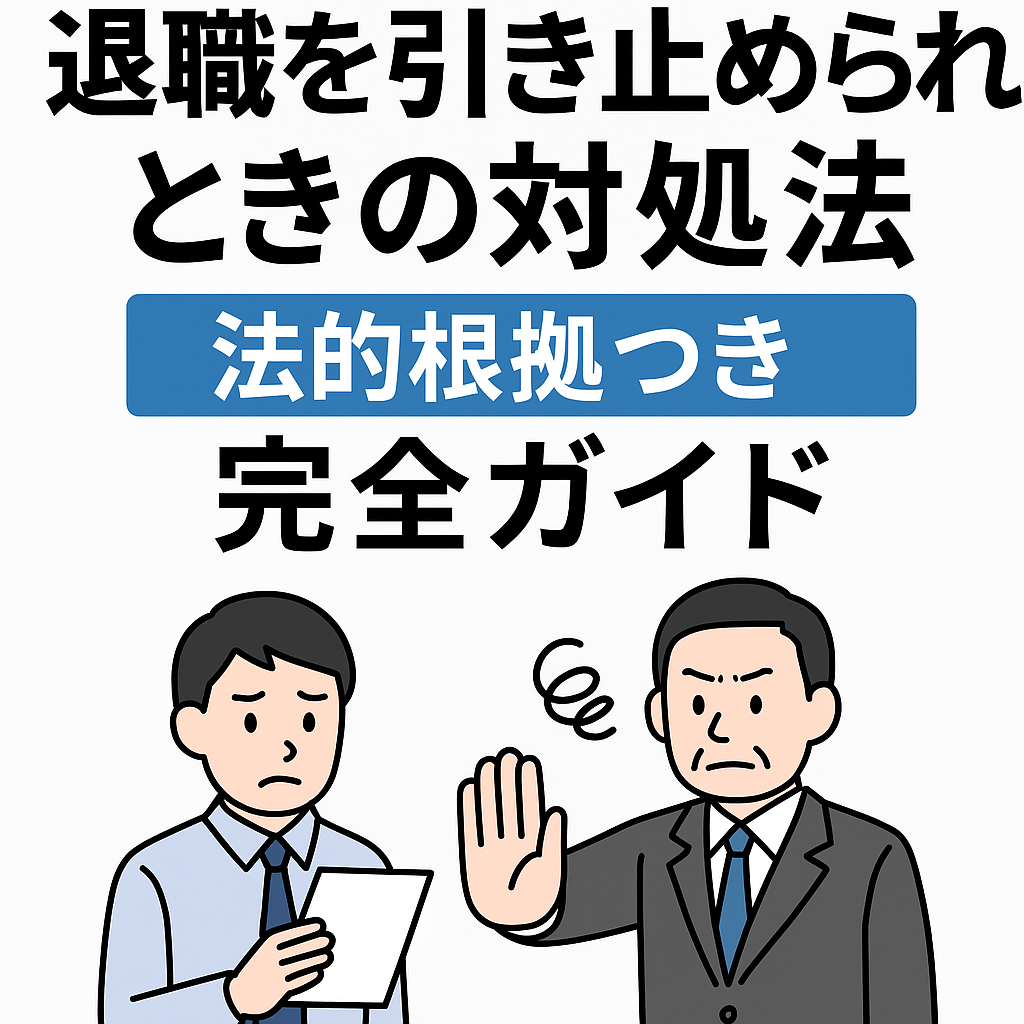
「人手不足だから今は無理」「繁忙期が終わるまで待って」――退職の意思を伝えたのに話が進まない。そんなときでも、退職はあなたの権利であり、法的ルールに沿えば確実に前へ進められます。本記事は、よくある引き止めパターンへの返し方、使える文例、そして根拠となる法律までをまとめた実践ガイドです。
結論の要点:無期雇用(期間の定めがない契約)なら、退職の申し入れから原則2週間で雇用は終了します。就業規則や上司の許可より法律が優先します。有期契約は例外あり(本文参照)。
引き止められる主な理由と考え方

- 人手不足を理由に退職を引き止められた時の対応:会社の都合。法的に退職を妨げる理由にはなりません。
- 就業規則で1か月前と書かれている場合の対処法:努力目標に近く、法律(2週間)に反する延長は強制できません。
- 評価・人間関係への圧力:感情論。事実と日付で淡々と進めるのが最短です。
- 有給は認めない:年次有給は原則労働者の権利。企業側に時季変更権はあるが乱用不可(後述)。
- 損害賠償・違約金の脅し:違約金の予定は禁止。実損の立証が必要で、むやみな請求は困難です。
引き止めにあっても、退職は法律で守られたあなたの権利です。安心して手続きを進めましょう。
まず整える「基本姿勢」5箇条

- 退職日を先に宣言:「退職日は◯月◯日(申し入れ日から2週間以降)です」と最初に明確化。
- 書面で残す:口頭→メール(PDF添付)→紙の順で証跡を積み上げる。受理の有無は効力に関係なし。
- 引き継ぎ計画を同封:具体的なToDoと日程を提示し、誠実さを可視化。
- 議事メモ:面談の日時・発言・対応期限を記録。必要なら内容証明郵便で意思表示。
- 感情論を避ける:法律と日付で淡々と。謝意は示しつつ軸はぶらさない。
ケース別:そのまま使える断り方テンプレ
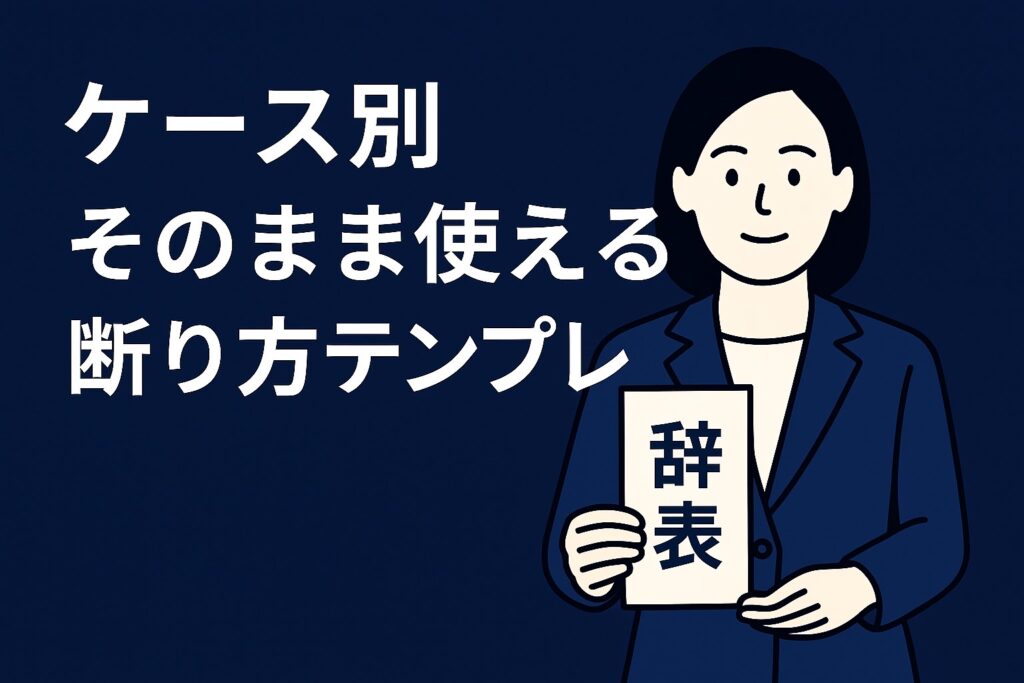
1)人手不足・繁忙期での引き止め
「ご迷惑をおかけしないよう、引き継ぎ計画(別紙)を提示します。退職日は◯月◯日で変更ありません。以降は有給消化の予定です。」
2)就業規則を理由に延期を迫られる
「就業規則は尊重しますが、法令上は退職の申し入れから2週間で雇用終了と理解しています。円滑な引き継ぎに努めます。」
3)有給を認めない・まとめ取りを拒否される
「業務に支障が出ないよう日程を調整済みです。ご懸念があれば、具体的な支障と代替案をご教示ください。」
4)損害賠償や違約金をほのめかされる
「労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償の予定は法律で禁止と理解しています。誠実に引き継ぎますので、具体的な実損があればご相談ください。」
退職を確定させる「証跡づくり」
- メール+PDF添付:退職届PDFを添付、送信ログを保存。
- 紙の退職届:社内提出。拒否されたら上位者・人事へ再提出。
- 内容証明郵便:受領の有無に左右されない意思表示。電子内容証明でも可。
ここだけは押さえたい法的ポイント
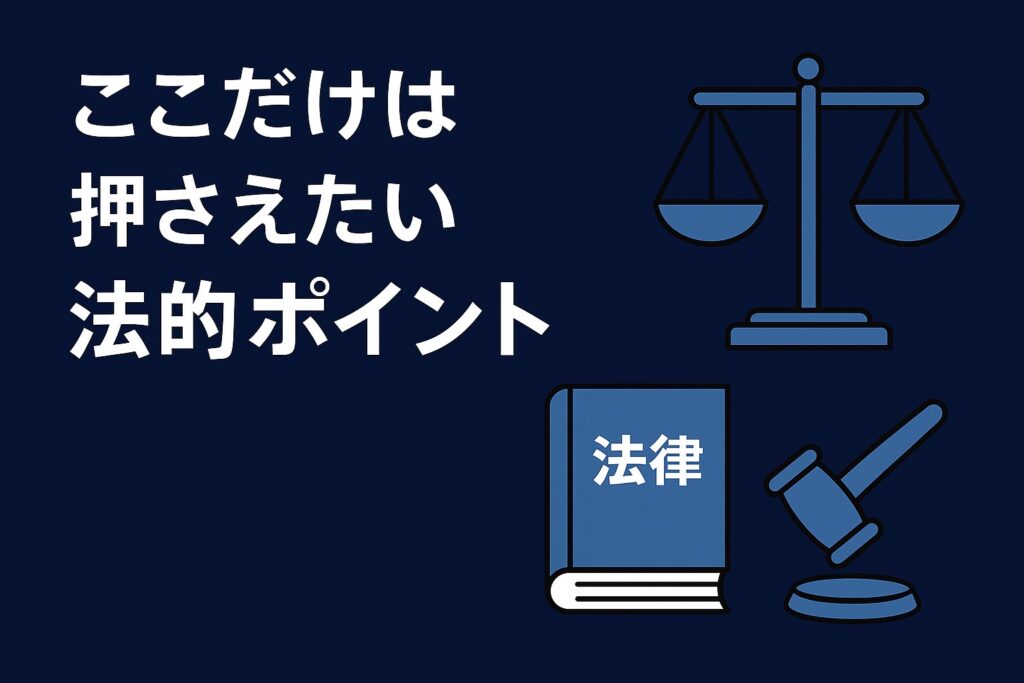
- 無期雇用の退職:退職の申入れから2週間で雇用終了(民法627条)。
- 有期雇用の途中退職:原則不可だが、やむを得ない事由があれば直ちに解除可(民法628条)。
- 有期でも1年以上:開始から1年経過後はいつでも退職可(労基法137条)。
- 違約金の予定禁止:労働契約の不履行に対する違約金・賠償予定は禁止(労基法16条)。
- 年次有給休暇:原則は労働者の時季指定。会社は事業の正常な運営を妨げる場合のみ時季変更権を行使可(労基法39条)。
- 「即日退職」表現の注意:当日から出社を止める運用は可能でも、法律上の退職日は原則2週間後(無期)です。代行は意思伝達の手段であって、法的期限を短縮するものではありません。
メール/退職届のひな形(短文)
件名:退職のご連絡(◯◯部 ◯◯)
◯◯部◯◯の◯◯です。私事で恐縮ですが、本日(◯/◯)をもって退職の意思をお伝えします。退職日は◯/◯(申入れから2週間以降)を予定しています。引き継ぎ計画を添付しました。何卒よろしくお願いいたします。
退職届(本文例)
退職届 私は一身上の都合により、◯年◯月◯日をもって退職いたします。
◯年◯月◯日/所属・氏名・押印
それでも難しいときの選択肢
関連記事
退職代行って本当に使うべき?迷ったらこちらへ。
退職代行のメリット・デメリット|失敗しない選び方と体験談
- 退職代行の活用:本人に代わって意思伝達。法定の2週間ルールはそのままです。交渉含む場合は弁護士対応のサービスを選ぶと安心。
- 公的窓口に相談:労働局の総合労働相談コーナーや労基署に早めに相談。
- 証拠保全:脅しや不当要求があれば、メール・録音・メモを保存。
まとめ|日付と書面で進めれば、必ず抜けられる
引き止めが強くても、退職日はあなたが決められるのが原則。退職日を示し、書面と記録を重ね、必要に応じて内容証明や公的窓口を使う。――この順序で進めれば、感情に振り回されずに確実に前へ進めます。
このページは概要です。今後、各パートの詳細記事(有給の時季変更権の具体例、代行の選び方、内容証明の出し方など)に内部リンクを追加していきます。
関連記事
退職代行って本当に使うべき?迷ったらこちらへ。
退職代行のメリット・デメリット|失敗しない選び方と体験談